環保協は、広島で環境調査や様々な検査・分析を行っている団体です |
||||
 |
||||
|
| |
|
|
|||
 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 私たちの周りにはいろいろな生物がすんでいます。有害な生物から希少種までさまざまな生物について情報を提供し、解決に向けた提案をしています。 お悩みの項目を選択してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■生物の名前を調べたい・異物を検査したい |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■衛生害虫・不快害虫の対策を行ないたい |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ビオトープをつくりたい |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■地域の自然を守りたい |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■自然観察教室を開きたい |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
名前の分からない生物や商品に混入した異物の検査を行い、由来などについても検討助言いたします。 このほか、顕微鏡で見るような小さな生物から、哺乳類や鳥類、藻類や樹木まで、さまざまな生物の名前を調べ、生態的な特性を明らかにします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 分析の手順: | 検体を検査室に持ち込み、図鑑類を参考に顕微鏡などを使用しながら、生物の名前や異物が何かを特定します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 結果の活用: | 生物の名前や異物の正体が判明したら、その生物の生態的な特性や異物の由来を調べ、由来を検討し、対策などを提案します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 不快害虫や衛生害虫の防除、施設の衛生管理に係る留意点など提案いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 分析の手順: | 検体を検査室に持ち込み、図鑑類を参考に顕微鏡などを使用しながら、生物の名前を特定します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 結果の活用: | 生物の名前が判明したら、その生態的な特性を調べて発生要因を推定し、進入経路や発生メカニズムを踏まえた対策や注意事項などを提案します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 関係法令: | 食品衛生法、公衆衛生法 |
|||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
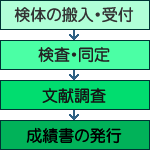 |
||||||||||||||||||||||||||
| 調査の手順: | 文献調査や現地調査により計画地の環境特性を把握し、整備前の生物相を把握または推定します。このような環境特性に応じて、新たに作り出すことが可能な環境要素(ため池・草地など)を特定し、その創出方法と維持管理に係る留意点を整理します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 結果の活用: | 設計、施工に反映し、効率的で効果の高いビオトープを実現します。また、ビオトープ供用後の説明にも活用します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 関係法令: | 広島県環境基本条例 |
|||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
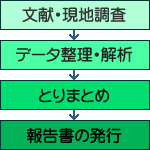 |
||||||||||||||||||||||||||
| 調査分析の手順: | 文献調査や現地調査により計画地が希少種の生息地かどうかを調べます。希少種の生息地であれば、その希少種の生態特性を踏まえて、事業の影響を緩和する方法と維持管理に係る留意点を検討します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 調査結果の活用: | 希少種への影響を緩和させる方法と維持管理に係る留意点を整理して設計に反映します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 関係法令: | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 文化財保護法 自然再生推進法 広島県環境基本条例 |
|||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
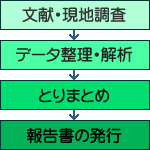 |
||||||||||||||||||||||||||
| 開催の手順: | 自然環境に関する知識と経験が豊富な講師を派遣します。 森林や耕作地、河川や海岸、市街地にいたるさまざまな自然環境について、あるいは対象者のニーズに応じて、適切な解説を行ないます。また、自然観察教室の企画運営も行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 事業の活用: | 児童生徒、一般住民の環境保全意識の向上など、地域貢献に役立てます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 関係法令: | 環境教育推進法 広島県環境基本条例 |
|||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
||||