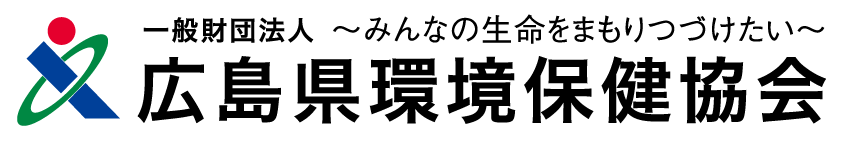ダイオキシン類分析
「ダイオキシン類」は、ごみ焼却等、燃焼による発生がよく知られています。その他にも製鋼用電気炉、鉄鋼業、自動車排ガスなど様々な発生源があります。人に対して、発ガン性や甲状腺や免疫の機能低下、生殖障害など様々な影響が考えられ、毒性の強い物質と考えられています。事業者の皆さんにとって、ダイオキシン類は取り扱いが憂慮される問題になることがあります。
当協会では各種現地調査の計画・実施および廃棄物コンサルタント等を行っております。お気軽にご相談ください
ダイオキシン類の測定について
ダイオキシン類汚染対策について
ダイオキシン類特別措置法について
ダイオキシン類の測定について
1.ダイオキシン類の測定について
「ダイオキシン類対策特別措置法」(公布:平成11年7月16日 法律第105号)は、ダイオキシン類対策における基本とすべき基準、必要な規制、措置等を定め、国民の健康の保護を図ることを目的としています。また、ダイオキシン類による環境汚染を防止するため、規制の対象となる施設を特定施設とし、施設ごとに排出基準を設定しています。
(参照:ダイオキシン類対策特別措置法について)
特定施設をお持ちの事業者の皆さんは、排ガス、排出水、廃棄物焼却炉のばいじん、燃え殻などに含まれるダイオキシン類の濃度を年1回以上測定し、都道府県知事に報告する義務があります。ダイオキシン類は、簡易測定法もあります。自主管理に際しては、簡易測定法の採用もご検討ください
2.ダイオキシン類の主な基準
ダイオキシン類は、その対象項目ごとに様々な基準が設定されています。ダイオキシン類対策特別措置法等による主な規制内容は、次表のとおりです。
| 項目 | 規制値等 | 規制内容 | 該当法令 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐容一日摂取量(TDI) | 4pg-TEQ/Kg/日以下 | 人の体重1kg当たりの1日の許容摂取量(Co-PCBも含めての許容摂取量) | 法第6条 | ||||
| 環境基準 | 大気 | 0.6pg-TEQ/m3以下 | ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準 | 法第7条 | |||
| 水質 | 1pg-TEQ/L以下 | ||||||
| 水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下 | ||||||
| 土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下 | ||||||
| 排出基準 | 排出ガス | 種類 | 新規施設 | 既存施設 |
特定施設の種類及び構造に応じて環境省令で定められている。 都道府県は、より厳しい排出基準を定めることができる。(区域を指定) |
法第8条 |
|
| 焼結鉱製造用焼結炉 | 0.1ng-TEQ/m3 | 1ng-TEQ/m3 | |||||
| 製鋼用電気炉 | 0.5ng-TEQ/m3 | 5ng-TEQ/m3 | |||||
| 亜鉛回収用焙焼炉 | 1ng-TEQ/m3 | 10ng-TEQ/m3 | |||||
| アルミニウム合金 | 1ng-TEQ/m3 | 5ng-TEQ/m3 | |||||
| 廃棄物焼却炉 | 4t/h以上 | 0.1ng-TEQ/m3 | 1ng-TEQ/m3 | ||||
| 2t~4t/h未満 | 1ng-TEQ/m3 | 5ng-TEQ/m3 | |||||
| 2t/h未満 | 5ng-TEQ/m3 | 10ng-TEQ/m3 | |||||
| 排出水 | 10pg-TEQ/L | ||||||
| 総量規制基準 | 都道府県知事が環境省令の定めにより総量規制基準を定める | 法第10条 | |||||
| ばいじん及び焼却灰の処分に係る基準 | 3ng-TEQ/g | 厚生省令で定める基準値以内 (処分するためのダイオキシン類濃度の規制) |
法第24条 | ||||
| 海洋汚染防止法によるばいじん及び焼却灰並びに汚泥の判定基準 | 3ng-TEQ/g | 厚生省令で定める基準値以内 (処分するためのダイオキシン類濃度の規制) |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項4号 政令(201)第5条第1項第10号及び11号 | ||||
|
余水吐きから流出する海水の水質基準 |
10pg-TEQ/L | 環境省令で定める基準値以内 (船舶から排出処分するためのダイオキシン類濃度の規制) |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項4号 政令(201)第5条第1項第10号及び11号 | ||||
|
廃棄物最終処分場の維持管理 |
放流水許容限度(10pg-TEQ/L) |
大気・公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることのないように環境省令で定める基準値に従う |
法第25条 |
||||
|
水底土砂に係る判定基準 |
10pg-TEQ/L(溶出濃度) |
海防法施行令第5条第2項に定める埋立場所以外への排出禁止及び海洋投入処分の禁止 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条 |
||||
ダイオキシン類汚染対策について
1.ごみ焼却炉でのダイオキシン類低減化
ダイオキシン類は、主にごみ焼却等、燃焼による発生がよく知られています。この、ダイオキシン類を焼却炉で低減させるためには、
- 1.ごみの焼却温度を800度以上とする。(既設の焼却炉では850℃以上、新設は900℃以上の維持が望ましい)
- 2.燃焼ガスを2秒以上滞留させる。
- 3.一酸化炭素濃度を100ppm以下とし完全燃焼させる。(既設の焼却炉では平均50ppm以下、新設は平均30ppm以下が望ましい)
ことが大切だとされています。
また、廃棄物の発生抑制(再使用、再利用等の推進)、ごみ処理の広域化(小規模な間欠運転炉を集約し全連続炉化)、焼却灰、飛灰の溶融固化等の無害化処理などを推進し、ダイオキシン類の発生を抑制するとともに、排出量を削減する措置を講ずる必要があります。
2.最終処分場の維持管理におけるダイオキシン類対策
焼却施設からの発生に次いで、周辺住民がダイオキシン類対策として不安に感じる事項に、最終処分場の維持管理に係る事項があります。
最終処分場の維持管理に係るダイオキシン類対策は、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」(平成12年1月14日総理府・厚生省令第2号)が定められています。これにより、浸出液処理設備の維持管理では、放流水の公共用水域への排出基準値として、10pg-TEQ/Lが設定されています。また、放流水および近傍の地下水中のダイオキシン類の濃度について測定が義務付けられています。この維持管理基準を遵守し、適正な最終処分場の運用を図ることが必要です。
3.港湾における底質ダイオキシン類対策
ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準が平成14年に告示され、これに併せて、同年、環境省から「底質の処理・処分等に関する指針」が通知されました。また、平成15年には、海洋汚染および海上災害の防止に関する法律が改正され、ダイオキシン類を含む底質を海面処分する場合、環境省令に定める溶出基準を超えるものは、一定の用件を備えた埋立場所以外への処分が禁止されました。
港湾整備あるいは浚渫の際に、このような底質のダイオキシン類汚染が確認された場合、その対策が必要です。平成15年、国土交通省により「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」がとりまとめられ、底質調査から対策工の選定、施工、処理・処分に至るまでの考え方、さらに工事監視およびモニタリングの技術的な考え方が示されています。
港湾は、汚染物質が堆積しやすく、船舶の航行や、工事に伴い底質のかく乱も生じやすいので、注意が必要です。
依頼方法
依頼書ダウンロードページは こちら